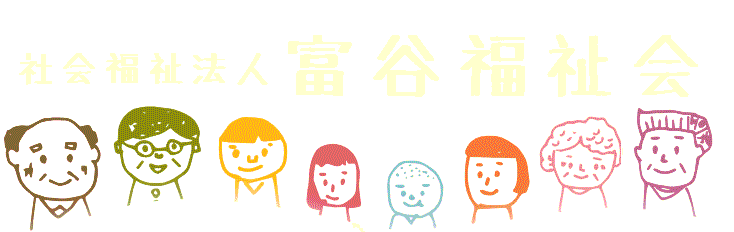かじりとる力
毎日の給食をおいしそうに食べる子どもたち。
子どもの年月齢によって、栄養士が提供の仕方(固さや形状など)を工夫しています。
保育士もまた給食を確認し、さらに一人ひとりに合わせて、小さくしたりして「食べやすく」するだけでなく、「食べる力が育つように」工夫しながら給食時間の保育を行っています。
とうもろこしはどんな風に食べる?
今日のメニューの「ゆでとうもろこし」
昨日、栄養士と保育士で、1歳児クラスのとうもろこしをどんな形で提供するか相談していました。
実を削いで食べやすい形にするか、芯に実がついた状態にするか。
今日は「芯に実がついた状態で」提供することにしました。
この形だと、子どもたちは実を「かじりとる」ことになります。
最初は、先生が持ったとうもろこしを「ガブ!」・・・芯まで食べてしまいそうな勢いの子も!
反対に「カプッ・・・」とかじりとれたかどうか分からないほど控えめな子も・・・

今度は自分で持って、上手にかじり取りながら食べていました。





子どもの噛んで食べる(咀嚼)力を育むためには、まず始めに「適量をかじりとる」ことができるようになることが大切です。
自分にとって「適量をかじり取る」ことができなけでば、うまく咀嚼することができず、丸飲みすることになってしまい、「のどに詰まる」原因にもなります。
いろいろな食材をいろいろな形で料理されたものを食べる経験を重ねていくと、だんだん上手になっていきますよ。
乳児の手づかみ食べの時期は、棒状にしたりかじりやすく咀嚼しやすいやわらかさにして練習していくといいですね。
★ただし、子どもの誤飲・誤嚥事故も多くありますので、お子さんの発達に応じて食べにくいものを小さく切って与えることは、事故防止の上で重要です。お子さんの口の動きや飲み込む様子をよく見ながら進めてくださいね。
~おまけ~
2歳児クラスのお友だちは、自分で上手に食べていました!